特定技能フィリピン人採用を成功させる!試験と採用メリットを解説

深刻化する日本の労働力不足に対応するため、在留資格「特定技能」制度に基づく外国人材の活用が企業にとって重要な選択肢となっています。中でも、若年層が豊富で、英語や日本語のコミュニケーション能力が高く、異文化への適応力に優れたフィリピン人材は、多くの企業から注目を集めています。
しかし特定技能の外国人材採用は、単に求人募集を行うだけでは成功しません。制度の複雑な仕組みや試験について、またフィリピン独自のプロセスや採用後の定着を促す支援体制などについて、十分な理解と戦略的な準備が求められます。
当記事では、フィリピン人特定技能人材の採用を検討している企業担当者向けに、試験を含めた採用プロセスや採用メリットについて説明します。さらに最新の制度変更や現場の声に基づく考察を通じて、企業がフィリピン人特定技能人材の採用を成功させ、長期的な戦力として定着させるための道筋を提示します。
特定技能制度の概要

特定技能制度は、日本国内で人材確保が困難な特定産業分野において、外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。外国人材が担う業務の熟練度に応じて、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれています。
特定技能1号
即戦力として業務をこなせる相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事します。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能2号
熟練した技能が求められ、現場のリーダーや監督者レベルの業務に対応可能な外国人を対象とします。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※特定技能2号は建設分野と造船・舶用工業分野の2分野に限定されていましたが、2023年の制度変更によって11分野にまで拡大されました。
特定技能1号と2号には対象分野や求められるスキルだけではなく、様々な制度上の違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 技能水準 | 指導者の下で作業 | 熟練技能でリーダー・監督的役割 |
| 日本語能力 | 試験等で一定水準確認 | 漁業と外食業分野のみJLPT・N3以上 |
| 義務的支援 | 必須 | 不要 |

特定技能1号の試験内容

特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として、従事しようとする分野ごとに定められた「技能評価試験」と、日本での生活や業務に必要な「日本語能力試験」の両方への合格が求められます。
分野別技能評価試験
各特定産業分野で求められる専門的なスキルや知識を測るための試験です。各分野ごとに定められた「特定技能1号評価試験」という試験に合格しなければなりません。
試験では実務に即した内容が問われ、その分野で働く上で必要な実践的技能を有していることが確認されます。
評価試験の実施時期や詳細については、こちらのサイトで確認なさってください。
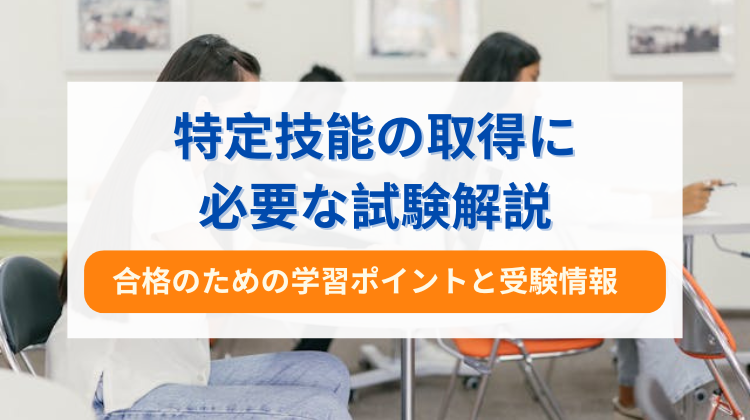
日本語能力試験
特定技能1号では、日常生活及び業務遂行に支障がない日本語力を証明することが求められます。次のいずれかの試験に合格しなければなりません。
| 日本語能力試験 (JLPT) | N4レベル以上の合格証明書が必要です。 |
|---|---|
| JFT-Basic (国際交流基金日本語基礎テスト) | 総合250点満点中200点以上で「日常会話ができ、生活に支障がない程度」と判定されます。 セクション別最低点設定はありません。 |
試験免除の特例:技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に修了し、当該実習職種と特定技能1号分野に関連性が認められる場合は、上記の試験が免除されます。
これは、実習を通じて既に必要な技能と日本語能力を習得しているとみなされるためです。
特定技能2号の試験内容

特定技能2号でも、1号と同じように必要な試験に合格しなければなりません。
分野別技能評価試験
特定技能2号の在留資格を取得するためには、各対象分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」への合格が求められます。
試験は学科および実技などで構成され、分野に応じた専門知識や技能を評価します。自社従業員が受験者となる場合には、事前に公式資料で手続きや範囲を確認し、案内なさってください。
日本語能力試験
特定技能2号の場合、原則として試験による日本語能力の確認はありません。これは制度上、特定技能1号から2号への移行が想定されており、ある程度の日本語能力を有していると考えられているからです。
ただし、以下の分野においては試験への合格が必要となります。
| 漁業分野 | 日本語能力試験(JLPT):N3レベル以上 |
|---|---|
| 外食業分野 | 日本語能力試験(JLPT):N3レベル以上 |
この2分野のみ日本語能力が要件となっているのは、外食業では言葉が通じないとサービスの質が低下し、クレームやトラブルの原因になるため。また漁業では、船上や港湾での危険な作業が多く、事故防止のために日本語で素早く正確に指示を理解する必要があるためです。
実務経験要件
特定技能2号の取得には、評価試験の合格に加え、一定の実務経験が求められます。これは、単に技能を有しているだけでなく、職場において他の作業員を指導・管理する能力を備えていることが期待されているためです。
求められる実務経験の内容や年数は、各分野によって異なります。

技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

2024年の入管法改正で創設された「育成就労制度」は、今後の外国人材戦略を検討するうえで重要な柱となるはずです。
なぜなら育成就労制度は従来の技能実習制度を見直して設けられた制度で、単なる技能移転ではなく、就労を通じた体系的な技能習得と長期的な人材確保を目的としているからです。
政府は2027年前後に育成就労制度の施行を予定しており、以後段階的に既存制度からの移行を進める運用方針を示しています。なお、具体的な運用細目は分野ごとに定められるため、事業者は最新の分野別運用方針を必ず確認してください。
育成就労→特定技能1号→2号:段階的キャリアパスの仕組み
育成就労制度の創設によって、外国人材に対する段階的なキャリア形成の枠組みがより明確になりました。想定される流れは概ね次のとおりです。
- 育成就労での育成期間(制度設計上は概ね3年を想定)に従事し、業務遂行能力を習得する。
- 育成過程で特定技能1号評価試験、ならびにJLPT・N4レベル以上などの要件を満たし、特定技能1号へ移行する。
- 特定技能1号としてさらに実務経験を積み、2号の要件(試験合格など)を満たすことで、特定技能2号へ移行可能となる。
この新しい制度によって「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」という段階的な登用を可能にし、企業が自社の業務・文化に合った人材を計画的に育てる事ができるようになります。
特定技能フィリピン人を採用するメリット

出入国在留管理庁の発表によると、特定技能制度を利用する外国人労働者の中で、フィリピン人はベトナム、インドネシアに次いで第3位の在留人数を有しています。
特定技能でフィリピン人を採用する5つのメリット
それだけ多くのフィリピン人が特定技能の分野で活躍しているのには、やはりそれなりの理由(メリット)があるからです。
メリット1:高い語学力
フィリピンでは英語を公用語の一つとし、多くの人が英語を流暢に話します。宿泊業や外食業など、インバウンド需要が高まっている日本において、即戦力となる人材です。また幼いときから複数言語の中で育つためか、新たな言語の習得も早い傾向にあります。実際に日本で働く多くのフィリピン人が早い段階で日本語を喋れるようになっているため、英語が苦手な人が多い職場でも円滑なコミュニケーションが期待できます。
メリット2:ホスピタリティ精神
フィリピン人は明るく陽気で、人とのコミュニケーションを大切にする国民性を持っています。またフィリピン文化に根付いた「おもてなし」の心は、特に介護分野や飲食料品製造、宿泊業などで大きな強みとなります。彼らが提供する質の高いサービスは、利用者からも高い評価を受け、企業の評判向上にも繋がるでしょう。
メリット3:親日的で日本文化への適応力が高い
フィリピンでは日本のポップカルチャーが広く浸透しており、日本に対して良いイメージを持つ人が多いです。そのため、日本の文化や生活習慣への適応が比較的スムーズに進む傾向があります。これは、職場での人間関係構築や定着率の向上において重要な要素です。
メリット4:優秀で学習意欲の高い人材の確保
フィリピン国外で働くことを選択するフィリピン人は、家族を支えたいという強い目的意識と向上心を持っています。新しい技術や知識、日本語の習得に対しても意欲的であり、企業の成長に貢献する優秀な人材となるポテンシャルを秘めています。
メリット5:特定技能2号への移行による長期就労の可能性
特定技能1号の自社外国人社員が特定技能2号に移行すれば、在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同も可能になるため、企業にとって長期的に安定した労働力を確保できるという大きなメリットがあります。


現場の声から学ぶ!特定技能フィリピン人活用のメリットと企業の支援体制

では、実際に特定技能フィリピン人を採用している企業の事例から、彼らを採用するメリットと、企業が取るべき支援体制について考えてみましょう。
岩手マイタックの事例(建設/土木)
東北の建設会社、株式会社岩手マイタックでは、フィリピン人特定技能者と技能実習生を毎年複数名採用し、定着率98%という高い成果を上げています。現場では即戦力として作業に貢献するだけでなく、経験を積んだ特定技能者が新人実習生の教育係となり、言葉や作業の違いをスムーズに橋渡ししています。
同社の代表は「企業は人がすべて。彼らはなくてはならない大事な戦力」と語っており、「生活に慣れてくると彼ら自身が次の代の面倒を見てくれるようになり、仕事の面でも率先して教育してくれます」と、彼らの存在を高く評価しています。
こうした信頼関係が、定着率の高さと教育効率化につながっているといえるでしょう。さらに、入社前から住居手配や生活サポート、日本語研修を用意し、安心して働ける環境を整えている点も定着の大きな要因となっています。
- 受け入れの仕組み化(住居・生活支援・日本語研修)が定着率向上の鍵。
- 経験者が新人教育の役割を担う仕組みを作ると、言語や文化の壁を超えやすくなる。
- 経営層が「彼らは大切な戦力」と明言し、職場全体に受け入れの姿勢を浸透させることが重要。
新来島サノヤス造船の事例(造船/製造)
造船業大手の新来島サノヤス造船では、フィリピン人特定技能者を採用し、溶接・造船技術をOJT(実地訓練)を通じて習得させています。
一人のフィリピン人従業員は「最初は日本語や技術に戸惑ったが、先輩や上司が段階的に支援してくれた」と語っており、会社側も「特定技能から2号へとつなげるキャリア設計を重視している」と明言しています。こうしたキャリアパスの提示により、モチベーションの向上と長期定着が実現しています。
- キャリアパス(特定技能1号 → 2号)を示すことが定着につながる。
- 業務に直結するOJTと定期的なフォローで、技能向上と不安解消が同時に進む。
参考:特定技能2号受け入れ事例紹介|G.A.コンサルタンツ株式会社
外食チェーンの事例(飲食/接客)
都内のラーメンチェーンでは、フィリピン人特定技能者を複数名採用。厨房と接客を分担し、業務内容をマニュアル化して指導した結果、店舗の接客品質が安定しました。
企業側は「フィリピン人スタッフの明るさとチームワークが接客現場にプラス効果を与えている」と評価し、フィリピン人本人も「マニュアルのおかげで安心して接客に挑戦できた」と語っています。その結果、離職率の低下や店舗の雰囲気改善につながっています。
- マニュアル化によって言語の壁を越え、品質を担保させる。
- フィリピン人の国民性(親しみやすさ・協調性)は、接客業で強みを発揮する。
これらの事例の通り、特定技能のフィリピン人材は「即戦力化」「現場の雰囲気改善」「教育の効率化」など、企業に大きな貢献を果たしています。
彼らが現場でその力を発揮するには、企業にも生活面の支援、日本語研修、明確なキャリア設計、社内での受け入れ体制の整備などが欠かせません。
特に紹介した事例に共通するのは「受け入れを仕組み化すること」で、これにより採用コストの回収と長期的な戦力化が現実的になります。

専門家によるビザ申請代行

特定技能外国人採用に不可欠なビザ申請発行手続きには、複雑な書類の準備を伴います。専門的な知識が必要であるため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請や申込みの代行業務を依頼しています。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
-
専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
-
煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。依頼料金がかかるとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
-
在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
-
申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

特定技能の在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となるのが注意点となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で特定技能1号として就労しているフィリピン人が2️号へ移行する場合には、MWOへの申請は不要です。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省
MWO申請サポートの手数料
MWO申請サポートでは、企業のニーズに応じて様々なサポートプランを提供しています。
| プラン名 | 主な内容 | 税抜料金 |
|---|---|---|
| フルサービスパック | 書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる | 98,000円 |
| 書類パックのみ | 英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプルなどの一式 | 45,000円 |
| 日本語サポートのみ | メール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など) | 45,000円 |
| 翻訳のみ | 日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入 | 45,000円 |
| 面接時通訳 | MWO面接時に立ち会う通訳者の手配 | 45,000円 |
※別途、MWOへの実費(書類認証手数料など)が必要となります。また提携送り出し機関以外を利用の場合、全プラン8万円追加となります。
フィリピン独自の複雑な手続きは、専門家のサポートを得ることで、企業側の労力を削減できます。
自社がどんな申請代行サービスを必要としているかを良く見極めて、依頼なさって下さい。
\ ご相談はこちらから /

まとめ:特定技能フィリピン人採用を成功に導くために

フィリピン人特定技能人材の採用は、日本の企業が直面する労働力不足に対する強力な解決策となり得ます。彼らが持つ高い日本語能力、異文化への適応力、そして就業意欲は、採用企業に多くのメリットをもたらすでしょう。
しかし採用を成功させるためには、特定技能制度への深い理解と、採用プロセス全体を通じた適切な支援体制の構築が欠かせません。
特にフィリピン人人材の採用には国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが不可欠です。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから /
