フィリピン人介護福祉士を採用するには?制度の概要・プロセスを解説

日本の介護業界は超高齢社会の進展に伴い、慢性的な人材不足という深刻な課題に直面しています。この状況を背景に、外国人介護人材は日本の介護現場を支える重要な存在となりつつあります。特に高齢者を大切にする大家族文化や、サービス精神、ホスピタリティの高さといった理由から、多くのフィリピン人が介護現場で活躍しています。
そうしたフィリピン人職員の多くは、技能実習または特定技能1号の在留資格で就労しています。しかしこれらのビザは在留期間の上限があるため、企業としてさらに長い期間雇い続けるためには、新たなビザへの切り替えを支援しなければなりません。
そのための有力な方法の一つが、介護福祉士の資格を取得することです。
介護福祉士となって在留資格「介護」を取得したフィリピン人職員は、在留期間の制限なく日本で永続的に就労できるようになり、企業と従業員双方に大きな利益をもたらします。
当記事では、フィリピン人職員が介護福祉士資格を取得するための要件とプロセス、そして企業が果たすべき具体的な役割について、包括的かつ実践的な視点から詳細に解説します。
国家資格「介護福祉士」取得がもたらすメリットと要件

介護福祉士国家資格の取得は、単なる個人のスキル向上に留まらず、企業の人材戦略と従業員のキャリア形成に多大な利益をもたらします。
フィリピン人従業員にとってのメリット
国家資格の取得は、フィリピン人従業員の日本での生活とキャリアに確固たる安定をもたらします。
- 日本でのキャリアと生活の安定
-
介護福祉士資格取得により、在留資格を「介護」に変更可能。在留資格の更新回数に制限がなく、長期就労が可能になります。さらに、5年以上「介護」で在留し、合計10年以上日本に滞在することで、永住権取得の可能性が広がります。
- 給与・待遇の向上とキャリアアップ
-
資格取得により、資格手当や基本給の引き上げが期待でき、無資格者と比べて収入増が見込めます。
- 家族の帯同が可能
-
在留資格「介護」では、配偶者と子どもの帯同が認められます。家族の同伴は従業員の精神的安定や生活基盤の確立に寄与し、結果として定着率の向上にもつながります。
- 介護のプロとしての自信と誇り
-
国家試験に向けた学習を通じて、根拠に基づく専門知識や体系的スキルが習得可能です。これにより従業員は自信を持ってサービス提供でき、介護の質向上にも寄与します。
企業にとってのメリット
フィリピン人従業員の資格取得支援は、企業経営にも多岐にわたるメリットをもたらします。
- 優秀な人材の長期定着と離職率低減
-
資格取得支援により従業員の定着率が向上し、長期的に安定した人材確保が可能になります。これにより、頻繁な採用や教育のコストを抑えられ、経営面での安定につながります。
- 外国人材のロールモデル創出と好循環
-
資格取得者が新人の指導役や相談役を担うことで、育成負担を軽減し、多文化共生の職場環境が促進されます。
- 介護サービスの質向上と介護報酬加算への対応
-
資格保有者の増加は、サービス専門性の向上と加算要件対応につながります。
介護福祉士国家試験の受験要件
技能実習生や特定技能で働く外国人が介護福祉士国家試験を受験する場合は、現場での勤務経験と研修を通じて資格取得を目指す方法が基本となります。
| 受験に必要な条件一覧 | |
|---|---|
| 実務経験(勤務期間) | 介護施設などでの勤務が3年以上(1,095日以上) 実際の従事日数が540日以上 特定技能1号や技能実習生は、在留期間内に条件を満たすことが可能です。 |
| 介護福祉士実務者研修の修了 | 約450時間(原則6か月以上)の研修を修了することが必須です。 働きながら受講するため、事業所の協力が重要です。 |
EPAによるフィリピン人介護福祉士採用の要点

外国人材の受入れには、いくつかの在留資格制度がありますが、フィリピン人の介護福祉士候補者の受入れにおいて中心的な役割を果たすのが、EPA(経済連携協定)に基づく制度です。
EPA制度の目的と在留資格「特定活動」の概要
EPA(経済連携協定)は、二国間の経済関係を強化することを目的とした協定です。EPAに基づく介護福祉士候補者の受入れは、現在、フィリピン、インドネシア、ベトナムの3か国に限られています。
来日する介護福祉士の候補者は、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」で入国し、受入れ施設で就労しながら国家資格取得を目指す形になります。
受入れ期間は原則として4年間の運用が基本で、一定の条件を満たす場合には規定を超えた1年間の滞在延長が認められることがあります。
EPAで来日する候補者の在留期間・更新・受験の流れ
来日後、候補者は日本語研修や介護導入研修を受けた後、受入れ施設で雇用契約に基づき就労・研修を行います。原則として在留期間は1年ごとの更新で、合計で原則4年を上限として運用されます。
日本での就労経験を通じて国家試験の受験資格を満たし、4年目または条件に応じて5年目に試験を受ける流れが一般的です。不合格の場合でも、一定の条件を満たせば1年間の滞在延長や、帰国してから短期滞在で再入国して受験するなどの例外的な運用が手引き上示されています。
資格取得後は、在留資格を「介護」に変更することができ、在留期間の更新回数に制限がなくなり、家族の帯同も可能となるため、日本での永続的な就労が可能となります。
EPA制度におけるJICWELSの役割
EPAによる介護福祉士候補者の受入れは、日本側で公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として統括しています。
JICWELSは、求人登録の受け付け、候補者と受入れ施設のマッチング、来日前後の日本語・介護研修の実施、そして来日後の巡回訪問や学習支援まで、一貫した調整と支援を担います。公的機関が中心となるため、受入れの手続きや基準に一定の厳格さと透明性が確保されています。
受入れ施設に求められる主な要件と期待される効果
受入れ施設には、適切な教育体制や指導体制が求められます。
たとえば、常勤介護職員に占める介護福祉士の割合や、養成施設と同等の実習体制を整えることなどが手引きで求められています。こうした基準に合致する施設のみが候補者を受け入れられるため、制度は量より質を重視した運用となっています。
結果として、来日前に基礎的な看護・介護教育を受けた候補者を確保できる点は、大きなメリットです。
運用上の注意点
EPA候補者の段階では、原則として家族の帯同は認められていません。
国家試験に合格して所定の手続きを経た場合、在留資格を「介護」等に変更できる可能性があり、その場合は家族帯同が可能になるケースもあります。
ただし在留資格の変更や家族帯同の可否は個別の審査事項であり、収入や住居などの生活基盤の要件が問われますので、制度上「必ず帯同できる」と断定するのは避けるべきです。
EPAの手続きや受入れ要件は厳格ですが、その分、質の高い候補者を安定的に確保できるという利点があります。長期的な視点で専門性の高い人材を育てたい法人にとって、価値の高い選択肢となるでしょう。
技能実習または特定技能からのキャリアアップ戦略

技能実習や特定技能1号で来日し、介護現場で働くフィリピン人は、介護福祉士国家資格を取得することで日本での長期的なキャリアを築くことができます。
技能実習から介護福祉士への移行ルート
技能実習では第1号から第2号で通算3年が基本ですが、介護分野においては第2号を良好に修了することによって第3号へ移行が可能です。その場合は通算で最長5年の在留が可能となります。
そのため、技能実習生のフィリピン人介護スタッフは、5年間の在留期間中に介護福祉士試験合格を目指せます。
ただし、第3号への移行は無条件ではなく、受入れ施設の要件を満たすことや監理団体の確認など、一定の条件をクリアする必要があります。そのため、企業は早期に長期的なキャリア形成プランを策定し、国家資格取得に向けた準備を進めることが重要です。
企業が取るべき実務的対応は以下の通りです。
- 勤務記録や業務内容の証明を厳密に残す(従業期間3年以上・従事日数540日以上の要件確認)
- 実務者研修(約450時間)の受講環境を整備し、勤務時間や費用負担の配慮を行う
- 日本語学習や業務日本語研修の提供、試験対策の支援
- 監理団体や送出し機関と連携し、第3号移行や特定技能への切替えの可否を確認
- 受験資格を満たせなかった場合の代替ルートも含めた計画策定
これらの対応により、自社の技能実習生フィリピン人スタッフの中長期的な人材定着と国家資格取得につなげることが可能です。
特定技能1号から介護福祉士への移行ルート
特定技能1号は通算で最長5年の在留が可能であり、技能実習に比べて国家資格取得までの期間に余裕があります。在留期間内に介護福祉士資格を取得し、在留資格を「介護」に変更することで、長期就労の基盤を確立できます。
資格取得に向けた企業の対応例は次の通りです。
- 入社時に資格取得までのロードマップを提示(実務日数・研修スケジュール・日本語レベル・試験申込み時期)
- 研修費用の一部負担や勤務時間の調整、学習支援の提供
- 業務内での専門用語や利用者対応のロールプレイ型研修
- 国家試験合格後の入管申請に備え、必要書類の整理(雇用証明・勤務実績・賃金台帳・住居証明など)
- フィリピン側送出し機関やDMWとの調整窓口を明確化
- 合格から在留資格変更までの期間管理と早めの申請準備
さらに、フィリピン人スタッフの状況に応じて、技能実習生→特定技能1号→介護福祉士という移行ルートも可能です。
ちなみに、在留期間に上限のない特定技能2号は現在、介護分野は対象外となっています。
参考:介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省

技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

2024年の入管法改正で創設された「育成就労制度」は、今後の外国人材戦略を検討するうえで重要な柱となるはずです。
なぜなら育成就労制度は従来の技能実習制度を見直して設けられた制度で、単なる技能移転ではなく、就労を通じた体系的な技能習得と長期的な人材確保を目的としているからです。
政府は2027年前後に育成就労制度の施行を予定しており、以後段階的に既存制度からの移行を進める運用方針を示しています。なお、具体的な運用細目は分野ごとに定められるため、事業者は最新の分野別運用方針を必ず確認してください。
育成就労制度をスタートとするキャリアパスの道筋
育成就労制度の創設によって、外国人材に対する段階的なキャリア形成の枠組みがより明確になりました。想定される流れは概ね次のとおりです。
- 基礎的な技能や知識を学び、職場環境に慣れる期間です。
- 即戦力として介護現場で従事します。
- 在留期間は最長5年で、介護分野は2号への移行はできません。
- 日本の介護福祉士資格を取得した場合に可能です。
- この段階で、在留期間の制限なく安定して就労できます。
育成就労制度の創設により、企業はフィリピン人介護スタッフを始めから介護福祉士として育てるという企業戦略をより取りやすくなるでしょう。
参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁
データと現場の声から紐解くフィリピン人採用のメリットと課題

フィリピン人介護人材の採用は多くのメリットをもたらしますが、同時に乗り越えるべき課題も存在します。客観的なデータと現場の声を分析することで、その実態を深く理解できるでしょう。
高い専門性と意欲
厚生労働省の調査データは、外国人介護職員の働きぶりに対する高い評価を裏付けています。EPA介護福祉士候補者から介護サービスを受ける利用者の84.2%が、その働きに「満足している」または「おおむね満足している」と回答しています。これは、フィリピン人が持つ親日性や勤勉さといった国民性と、介護分野での専門教育が結びついた結果といえるでしょう。
また、受け入れ施設側の評価も同様に高く、「大変仕事熱心であり、高く評価できる」と回答した法人は、EPA介護福祉士候補者に対して49.2%に上ります。
これらデータは、彼らが日本の介護現場で高い学習意欲と専門性への期待に応える働きぶりを示していることを物語っています。
参考:外国人介護人材の介護現場における就労実態等に関する調査研究事業 |厚生労働省
日本語の壁という課題
一方で、外国人介護人材が乗り越えるべき大きな課題として、日本語の壁と国家試験の合格率が挙げられます。第37回介護福祉士国家試験における外国人受験者全体の合格率は30%台であり、日本人受験者を含む全体の合格率78.3%と比較して低い傾向にあります。特にフィリピン人候補者の合格率は22.8%と、ベトナム人候補者の84.3%と比べると大きな差が生じています。
この合格率の差の背景には、入国要件として求められる日本語能力の違いがあると考えられます。フィリピン人候補者の入国要件は日本語能力試験N5程度と比較的低い一方、ベトナム人候補者には実質的にN3以上が求められています。
現場で働くフィリピン人介護職員は、日本語でのコミュニケーションに問題はなくても、「読み書き」に難しさを感じることも多いようです。実際に厚生労働省の調査でも、外国人介護職員の86.5%が「日本語が難しい」、81.7%が「介護の言葉が難しい」と感じていることが示されています。
これらの事実から、日本語能力と国家試験合格率には直接的な因果関係があり、この課題を克服するためには、入国後の継続的かつ実践的な日本語研修が不可欠であることがわかります。
企業は、候補者が国家試験の学習や現場での円滑なコミュニケーションを十分にこなせるよう、職場でのOJTを通じた実践的な日本語・介護用語の教育支援体制を構築することが、合格率向上と定着の鍵となるでしょう。
参考:第37回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果|厚生労働省

実際の成功事例とそこから学ぶべき教訓

実際に日本で活躍しているフィリピン人介護福祉士の生の声からは、採用成功に向けたより深い学びが得られます。
介護福祉士の資格を取得したクリスティーナさんの事例
フィリピン人のクリスティーナさんは、留学ビザで来日後、日本語学校に通いながら介護施設でアルバイトを続けていました。来日当初の日本語能力はJLPT N4程度で、職場の指示や会話を理解するのに苦労していたといいます。
しかし、職場のスタッフは常に丁寧に説明やアドバイスを行い、生活面での困りごとにも耳を傾けてくれました。クリスティーナさん自身は「仕事の合間にわからないことを気軽に相談できる環境があることで、自信を持って働けました」と語っています。
彼女は一時期、給料の高い他施設への転職も考えましたが、最終的には「サポートが手厚く、安心して働ける今の職場で長く働きたい」と決断しました。さらに、職場の支援を受けながら介護福祉士実務者研修を修了し、国家資格試験に挑戦。見事、合格を果たしました。
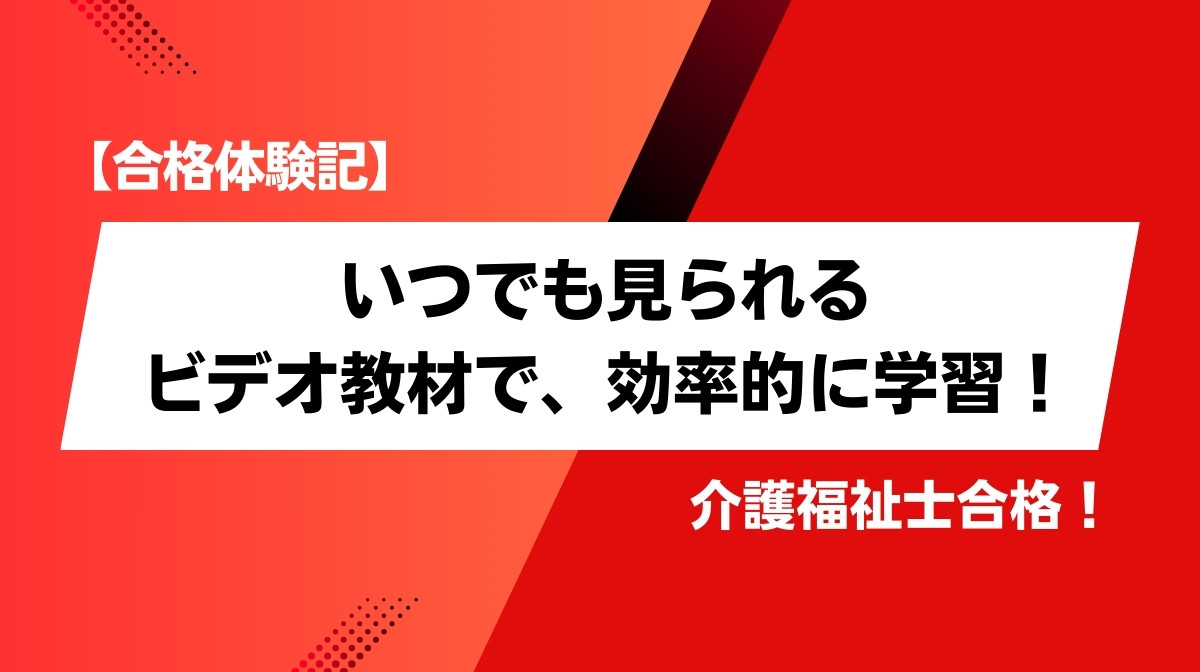
学べる教訓:企業が取るべき支援策とは?
クリスティーナさんの事例から学べる、企業が取るべき支援策は以下のとおりです。
- 日常業務での相談体制の確保
- 職場で困ったことや不安を気軽に相談できる環境は、外国人材の安心感と定着意欲を高める。
- 実務経験と研修の両立支援
- 国家資格取得には実務経験と実務者研修の修了が必要です。勤務時間の調整や研修費用の補助など、学習支援の提供が重要です。
- 生活面のフォロー
- 住居や生活上の困りごとへの対応、職場内でのコミュニケーションサポートが、長期雇用の基盤になります。
- 資格取得のサポート
- 日本語や介護用語の学習支援、模擬試験や個別指導の提供が、合格率向上につながります。
これらの支援は給与や待遇だけでは補えない部分であり、手厚いサポート体制は外国人材の定着とキャリアアップに不可欠です。
参考:【スタッフインタビュー】フィリピン人介護士クリスティーナさん!介護ビザを取得し日本で働く | 株式会社スタッフ満足
MWO申請|フィリピン人材の受け入れのために

フィリピン人材を新たに国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、介護スタッフとしてフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
すでに日本国内で技能実習生や特定技能1号として就労しているフィリピン人が介護福祉士国家試験に合格し、新たなビザを取得する際には、基本的にMWOへの申請は不要です。しかし、雇用主が変わったり、一時帰国を挟む場合などには、MWOへの申請が必要となる場合もあります。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類や資料に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

MWO申請サポートの手数料
MWO申請サポートでは、企業のニーズに応じて様々なサポートプランを提供しています。
| プラン名 | 主な内容 | 税抜料金 |
|---|---|---|
| フルサービスパック | 書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる | 98,000円 |
| 書類パックのみ | 英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプルなどの一式 | 45,000円 |
| 日本語サポートのみ | メール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など) | 45,000円 |
| 翻訳のみ | 日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入 | 45,000円 |
| 面接時通訳 | MWO面接時に立ち会う通訳者の手配 | 45,000円 |
フィリピン独自の複雑な手続きは、専門家のサポートを得ることで、企業側の労力を削減できます。
自社がどんな申請代行サービスを必要としているかを良く見極めて、依頼なさって下さい。

まとめ:フィリピン人介護福祉士との共創で築く未来

フィリピン人介護福祉士の育成は、日本の介護現場が直面する人材不足の解決に大きく貢献する有効な手段です。彼らの持つ勤勉さや専門性、そして家族を大切にする文化は、日本の介護サービスに新たな活力を与えるでしょう。
採用を成功させるためには、日本の在留資格制度だけでなく、フィリピン独自のMWO申請手続きを正確に理解し、対応することが不可欠です。これらの複雑な手続きを乗り越え、彼らを迎え入れた後も、文化的な配慮、継続的な日本語教育、そして明確なキャリアパスの提示を通じて、彼らと「共創」する組織づくりを目指すべきです。
MWO申請サポートでは皆様のニーズに応じた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから /
